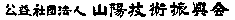|
2024年4月1日 発信 |
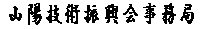 Tel.(086)454-8820/Fax.(086)454-8821 | |
| 2024.01(Apr.2024) |
 | |
|
・山陽技術振興会第79回通常総会
| |
|
令和6年5月31日(金)13:00~14:00、場所:倉敷商工会議所 (1)総会13:00~14:00、(2)令和6年度第1回理事会:令和6年5月31日(金)14:00~14:30
| |
|
・山陽人材育成会総会・講演会 | |
|
令和6年5月31日(金)15:00~、場所:倉敷商工会議所、講演:鈴木康幸氏[消防研究センター長・元消防庁審議官]
| |
|
・山技振サロン、技術交流会、工場見学会、は引き続き休止。 | |
 | |
|
・山陽技術振興会令和5年度第3回理事会
| |
|
日時場所;令和6年3月12日(火)18:30~19:30於倉敷商工会議所、出席者;理事26名中15名出席、監事1名出席。会長業務執行報告。第1号議案;令和5年度事業報告、第2号議案;令和5年度収支決算報告、①基本事業収支決算、②人材育成事業決算、第3号議案;令和6年度活動方針・事業計画、第4号議案;令和6年度収支予算計画、[①基本事業、②人材育成事業、③公益法人事業]、第5号議案;研修室資金積立額決定、第6号議案;定款一部改訂[役員定員、ほか]、第7号議案;役員改選(改選期)、第8号議案 事務所移転(美和事務所は3月末を以て閉鎖、山陽技術振興会の所在地は倉敷市水江170番地となる。) Ⅰ 令和5年度の事業報告と決算 1.総会、役員会、2.委員会、3.技術振興事業(講演会、山技振サロン、技術交流会、工場見学会)は、総会講演会のみ実施、4.人材育成事業は17年目で、受講者は2,701名でコロナ禍前を超えた。増収増益で研修室資金に300万円を計上。5. [技術普及事業];技術情報提供(“山技振たより”は当面継続、“山陽技術雑誌”は休止)、村川難波技術奨励賞終了、山陽技術賞保留、文部科学大臣賞・県知事賞推薦継続。[顕彰事業]:岡山県生徒児童発明工夫展・未来の科学の夢絵画展継続、岡山県児童生徒科学研究発表会継続、ロボコンジュニア大会中止。【以上審議、提案通り可決】 Ⅱ 令和6年度の事業計画と予算、定款一部改訂、役員改選、事務所移転。『基本事業』は、会員減・収入減・事務所移転を機に事業見直しを実施、技術振興事業の大部分は休止継続、技術普及事業は当面継続するが近い将来ソフトランディングを図る。6月会費請求時に分かり易い説明書を同封予定。事業見直しにより会員減・会費収入大幅減が予想され、自立困難。『人材育成事業』は18年目を迎え、安定収入6,000万円を目標に努力し、新講師・新講座発掘、出前講義拡大、新カリキュラム開発等で継続・発展を目指す。今年は役員改選年で、事務所移転に伴う基本事業の見直しを機に役員人事の大幅変更を提案。総会で理事承認後の第1回理事会で会長、副会長、事務局長を決定。定款一部改訂(理事定員、ほか)の件。事務所移転の件。【以上につき審議、技術普及事業サービスについて質疑(→退会後も当面サービス継続予定)、議案全般につき討議、提案通り承認・可決。】 | |
|
・人材育成事業
| |
|
令和5年度は開業17年目にあたる。年初、コロナ禍の影響を踏まえオンラインを前提に募集をした。事業全体では人材教育への期待とリモートの利便性が相乗し、受講者はコロナ前の状況を超える数となった。すなわち、年間では出前・共催コースを25講座とホームコース74講座を合わせ99講座を実施し、延べ受講数は2,701名でコロナ前の2019年を超えた。その結果、事業収益は予算に対し518万円増の6,183万円と増収となり経費を差引いた経常損益は312万円の増益となった。このうち300万円を研修室資金に積み立てることとする[理事会承認を要す]。
| |
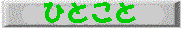 | |
| 「カマキリとその仲間たちの成長と生活の記録 part3」里庄東小学校3年国定旺太郎 | |
| 事務所移転の最中に郵便物が来た。内容は「科研報告書」とある。不審に思い開けて見た。第73回岡山県児童生徒科学研究発表会の報告書である。山陽技術振興会会長賞を授与した掲記の里庄東小3年国定君の1年間に亙るカマキリ研究のカラー写真入報告書で、なかなかの出来栄えである。part3とあるのでpart1、part2は小学校1~2年生時に研究したと思われる。課題を取り上げた動機は「①カマキリが大好きだから」が一番に挙げられている。「④カマキリが餌を捕まえる動きにとても興味があったから」、「⑤カマキリの脱皮の様子に興味がわいたから」、私も同感である。「②『高いところに産卵すると大雪が降る』説は正しいのか?」、「③卵から育てたオス・メスを交尾させて二世が生まれるか?」、「⑥カマキリには『なわばり』があるのか? オス・メスを同じ籠に入れて交尾の様子をつぶさに観察した記録は圧巻である。3組中2組は無事交尾を終えてすぐ別な籠に移したのでオスは無事だったが、一組は交尾する前にメスがオスの翅のつけ根に噛みついて、むしゃむしゃ食べ始め、1時間後にはすべて食べつくした。床に食べかすが落ちていた。カマキリが家庭菜園のどの野菜に集まるか(餌の待伏せ)の観察もなかなか面白い。カマキリが餌を捕まえる行動と認識(視認?匂い?)と捕獲距離、成虫になるまでに7~8回脱皮するときのポーズ、等々である。こうした「観察力」は、大人も子供もなくセンスが支配するものの様である。私も小学生の頃、夏柑の幹で鳴いているクマゼミをカマキリが襲う場面を目撃した。カマキリは、セミが鳴いている幹の裏側を通って真裏に回り込み、体を軽く左右に揺らした次の瞬間、幹の反対側に回り込み、クマゼミを羽交い絞めにして一体で地面に落ちる。セミは絶叫するが、やがて静かになる。【kajix】 | |