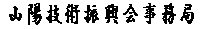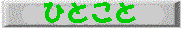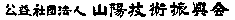古くからの山技振会員にとっては最後の山陽技術振興会総会が開催された。来年度からは事業内容が大幅に変更となり、人材育成会会員と山技振会員が合併して新山技振会員に生まれ変わる予定である。今年から会費徴収ルールを変更した。6月には多くの会員に会費請求書と退会届の両方を送付するのでどちらかを選択して頂きたい。退会しても文科大臣表彰・県知事表彰推薦等の技術普及事業サービスは継続する。
 |
・公益社団法人山陽技術振興会第79回通常総会報告書、令和6年度第1回理事会報告書、役員名簿等を法務局ならびに岡山県産業労働部宛提出。
|
・山技振サロン、技術交流会、工場見学会は引き続き休止。
|
 |
・公益社団法人山陽技術振興会第79回通常総会
|
|
令和6年5月31日(木)13:00~14:00、場所:倉敷商工会議所 (1)総会13:00~14:00、(2)理事会:14:00~14:30。第1号議案 令和5年度事業報告、基本事業:技術振興事業は休止状態が継続、技術普及事業は従来通り活動。人材育成事業は開業17年目、コロナ禍前のレベルを回復。第18回村川・難波技術奨励賞は基金尽きて終了。第2号議案 令和5年度決算報告:基本事業は収入減を経費削減で切抜け、人材育成事業は受講者数回復で大幅収益増となったが事務所移転・講義室機能拡充等への支出もあり、研修室基金への預入は300万円とした(3月理事会で承認)。雀部監事が監査報告。第3号議案 令和6年度活動方針と事業計画:基本事業は、技術振興事業の一部休止、技術普及事業は継続実施の計画とした。人材育成事業は18年目、受講数増を予想、講座のさらなる高度化と多様化を進める。第4号議案 令和6年度収支予算:基本計画は縮小、人材事業は拡大基調。第5号議案 研修室資金積立額 理事会決定額300万円を報告・承認。第6号議案 定款一部改訂[役員定員、ほか]提案通り承認。第7号議案 役員改選(改選期):理事定員15名に変更され、理事11人、監事2人が提案通り選任された。第8号議案 登記住所変更 令和6年4月1日法務局登記住所(倉敷市水江170番地)が承認された。
|
・令和6年度第1回理事会
|
|
令和6年5月31日(木)14:00~14:30:総会に引続き開催。互選により、会長梶谷浩一、副会長 植田章夫、太田巧、内野一人を決定。全員から抱負と要望を発言。
|
・山陽人材育成会総会・表彰式
|
|
令和6年5月31日(木)15:00~16:10、場所:倉敷商工会議所、2023年度実績と2024年計画、年度末に人材育成会の山技振事業への編入計画説明・承認、山陽人材育成講座2万人目受講者の表彰・優秀講師表彰。1615~記念講演:鈴木康幸氏[総務省消防研究センター所長・元消防庁審議官]、演題「正当にこわがることはなかなかむつかしい」。
|
・名刺交換会
|
|
令和6年5月31日(木)17:30~18:30、鈴木康幸氏ほか、約40名参加。
|
・人材育成事業
|
|
令和5年度は、人材教育への期待とリモートの利便性が相乗し、受講者数はコロナ前を超えた。令和6年度は、現時点で46事業所からホーム87・出前仮予約20、合わせて107講座に2816名の受講希望者があり、昨年を超える予想で、内2/3が対面予定(やはり対面がいい?)。
|
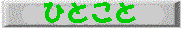 |
| 「弁理士法人 森特許事務所」
|
|
昭和40年代からの山技振会員である森廣三郎氏が総会に出席され、一番前の席に座られた。森さんは1933年生れの91歳で、今なお現役弁理士である。古い会員の顔ぶれが見られる最後の機会との前宣伝が伝わったものと思われる。総会終了後にお土産を頂いた。「生まれる発明 育てる弁理士」-わが弁理士人生に寄せて-と題する137頁の大冊子である。この中に、山陽技術振興会のことも書かれている。森さんは、倉敷レイヨン㈱在職中に上司の勧めもあって昭和41年に弁理士資格を取得し、数年を経て独立し、倉敷市郊外の自宅に特許事務所を構えるのである。独立に当たって、当時の上司には強く引き留められたが、もう一人の上役であった安井昭夫主研(当時)には「男がいったん言い出したら引っ込めるわけにはいかん、引き留めるのはナンセンスだ」と正論を述べられ、“特に許してもらう”ことになった由である。山陽技術振興会は、岡山県内2つ目の「特許公報閲覧所」であり、全ての特許公報分冊が無料で閲覧できる場所で、書架がずらりと並び、その重さで床板が抜けて書架が傾いたままになっていた。山技振事務所は、1998年に美和に移転するまでは現在のアイビースクエアのフローラルコートの辺りにあったのである。地場企業の古参の方々からは「山技振の特許閲覧所のお陰でウチは大変助かりました!」と再三言われた。大原總一郎が山陽技術振興会を設立した大きな目的は「中央との情報格差是正」であった。講演会・技術交流会、特許閲覧所は、その象徴である。特許公報に関しては、美和事務所に移って間もなくCD-ROMになり、有料ネット検索(山技振は無料)になり、ついに無料ネット検索になった。特許情報格差はなくなったというべきである。講演会に象徴される技術情報格差についても、コロナ禍を契機にWEB上で見れる動画が格段に多くなった。隔世の感がある。にもかかわらず「生まれる発明、育てる弁理士」というFace-to-Faceの重要性は失われていないのであろう。森さんの書き物を見ながら様々なことを思い出した。【kajix】
|