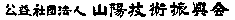|
2024年10月1日 発信 |
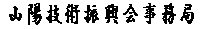 Tel.(086)454-8820/Fax.(086)454-8821 | |
| 2024.07(Oct.2024) |
 | |
|
・10月 8日:有隣会常任世話人会 ・10月15日:岡山大学工学教育外部評価委員会 ・山陽技術振興会第2回理事会:2025年3月6日(木)(仮) ・山陽技術振興会総会:2025年6月2日(月)(仮) | |
|
・人材育成事業主要会議予定:
| |
|
(1)10月中:来年度講座シラバス提出(講師)、講座スケジュール案、企業訪問資料作成。企業訪問開始 (2)12月6日(金)第70回担当者会議:2025年度講座スケジュール確定、次年度総会日程等決定 (3)2025年1月31日第34回AB会議:2025年度講座計画と3講座の講師交代報告予定 (4)2025年3月6日(木)71回担当者会議(2024決算予想・2025年度予算案) | |
 | |
|
・「岡山県工業技術開発功労者賞」推薦(10/4締切):会員外企業案件の助言修正を経て担当課に提出。 ・第69回担当者会議:8月29日(木)台風接近のためリモート開催。2025年度計画を仮決定。「ものづくり日本大賞」と「山陽技術賞」とのリンクを提案。 ・2講座同時開催試行:9月17日(月)に初めての試みとして対面講座(岩間講師)とリモート講座(山田講師)の2講座同時開催を試行、課題の発見と対応策を検討中。 ・受講環境整備:9月より受講生デスクのICT機器のコードレス化を進めている。 ・9月末現在出前8を含む63講座(45は対面)を実施、延1652名が受講。2024年度通期見通しは、29科目でホーム86講座と出前予約19講座、合計105講座に昨年を超える2765名が受講の見込。経常外費用として研修室拡張と会議室整備合計500万円を検討中。 ・出前講座の動向:旭化成(4+3)、クラレ(6)、大分県(2)、日本触媒(3)、レゾナック大分(0) | |
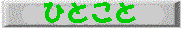 | |
| 独立研究者「森田真生」 | |
| 書店の雑誌コーナーで何気なく手にした「新潮」10月号になつかしい名前を見つけた。“独立研究者森田真生”さんである。8年前に有隣会記念講演会で「数学を通して人間を考えるー岡潔と数学の“情緒”―」の講演を頂いた。森田さんは、その前夜周防大島で「演奏会」(聴衆とのワークショップをこう呼ぶ)を終えた由だったが、倉敷市民会館の舞台上を端から端まで速足で歩きながら話し続けた。講演後の会食でも地元の同世代と盛り上がり、年寄組が去った後も日付が変わるまで交流が続いた由であった。幼少期をシカゴで過ごし、近くに住んでいたマイケル・ジョーダンの影響でバスケットボールに目覚め、桐朋中学・桐朋高校でバスケットボール部に属し、高校ではキャプテンを務めた。2004年東大文Ⅱに入学、ITベンチャーの人々にも興味を持ち、理系に興味を抱き工学部システム創成学科に転部、卒業後さらに理学部数学科に学士入学、卒業後2010年福岡県糸島市(新朝ドラ“おむすび”の舞台)に数学道場を設立、2012年に京都市鹿が谷に移り、在野で研究活動を行い(独立研究者)ながら、「数学の演奏会」や「大人のための数学講座」、「岡潔による芭蕉論」などのライブ活動を全国で行っている。数学者岡潔をこよなく敬愛し、岡潔が奈良女子大学を早期退職して野良仕事をしながら論文を発表し続け、現代のデジタル社会に必要な概念を提案する論文もあったという。森田真生が“独立研究者”を自称するのは、尊敬する岡潔の生き方の影響である。初の単著「数学する身体」(2016)で最年少の小林秀雄賞、「計算する生命」(2022)で河合隼雄学芸賞を受賞、その他著書多数。岡潔著「数学する人生」(新潮社)の文庫化に際し、森田真生が編集に関り増補を行った。【対談「父、岡潔の思い出」森田真生VS.松原さおり(岡潔の次女で貴重な資料を保存し、希代の数学者の言葉を次世代につなげてきた松原さおりさんに、本書編纂を務めた独立研究者森田真生氏が聞く!)。】 森田真生「数学する惑星」第一回「地球の言葉で考える」新潮2024年10月号(新潮社) 『八歳になった長男がまだ四歳の頃、なぜか突然突然真顔になって「木星に行きたい!」と言い始めたことがあった。ちょうど新型コロナウイルスの世界的な流行が始まったばかりの頃で、子どもたちと自宅にいた僕は、さっそく木星について解説している動画を一緒に探した。待ち切れない様子で動画を見始めた彼だったが、「厚さ1000キロメートルほどの大気の底は、あまりの高圧のため、水素が液体に状態を変えている」というナレーションが流れてくると、僕の膝の上でぼそっと「行かない方がいいかな・・・」とつぶやいたのだった。大気の組成や気圧は、惑星ごとにそれぞれ特徴があって、少なくとも地球の近くには、地球に似た大気をもつ惑星はない。宇宙のなかで見れば、地球の空気ほどめずらしいものはない。あのとき息子は、想像していたのとは違う木星の「空気」を感じて、心細い気持ちになったのかも知れない。』(この連載で、人間だけのための言葉ではなく、「地球の言葉」で考え始める練習を始めると述べている。期待したい。) [kajix] | |