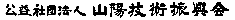|
2023年1月1日 発信 |
 Tel.(086)422-6655/Fax.(086)422-6656 | |
| 2022.10(Jan.2023) |
 | |
|
・技術交流会:他の団体と相乗り開催することにしました。 | |
| 日時:2023年2月15日(水)15:00~17:00、場所:水島愛あいサロン(水島臨海鉄道水島駅前)、講演1「ウェルエイジングに老年スポーツを」講師:三宅雅(倉敷中央病院)、講演2.「南極観測を支える」講師:中藤琢雄(南極観測船「しらせ」元艦長)、参加費:1000円 | |
|
・令和4年度第2回理事会(予定表に記入して下さい) | |
|
日時:令和5年3月28日(火)18:00~19:00(懇親会なしの予定) 於倉敷商工会議所【詳細は2月確定】 | |
|
・令和5年度第1回理事会日時【仮日程】 | |
|
令和5年5月25日(木)14:00~15:00、場所:倉敷商工会議所 | |
|
・山陽技術振興会第78回通常総会日時【仮日程】 | |
|
令和5年5月25日(木)15:00~17:30、場所:倉敷商工会議所 (1)総会15:00~16:00、(2)村川・難波技術奨励賞表彰式、(3)記念講演16:30~17:30【未定】 | |
|
・村川・難波技術奨励賞 | |
| 第18回「村川・難波技術奨励賞」募集、締切1月末。詳細は当会に問い合わせるか、当会HP「村川・難波技術奨励賞」の項参照。賞金10万円を2件に贈呈。 | |
|
・「山陽技術雑誌Vol.71」原稿募集 | |
| 締切は1月末。各社広告も募集します。1頁はB5判、2,208字(原則24字×46行×2列)白黒印刷。当会会員・広告主および企業・研究所・大学・国会図書館など約200ヶ所に送付。 | |
|
・川崎医科大学KMSメディカル・アーク2023(山技振後援) | |
| 開催日・時間2023年2月8日(水)12:00~16:00[オンライン開催]、[事前申し込み要] | |
|
・人材育成事業 | |
| (1)1月31日AB会議:2023年度講座スケジュール確認およびインボイス制度の概要説明。講師に不利益が生じない対応説明。(2)企業訪問:1月に加速実施予定 | |
 | |
| ・『生徒児童の顕彰事業』岡山県児童生徒科学研究発表会・表彰式 | |
| 12月4日(日) 9:20~於岡理大 表彰式非公開実施、山技振会長賞を4名に授与【①岡山市立綾南小学校村山史煌「かなへびはなんじにねているの?」、②岡山市立千種小学校信近耕汰「水生昆虫の観察」、③ 真庭市立木山小学校平内心遥「今!!大切な人を守るために必要なこと第2弾」、④岡山大学教育学部付属中学校樋口碧一「風を遮る物の種類によっての風の通り方の変化」】 | |
| ・ロボカップジュニア2022岡山ブロック大会 in ライフパーク倉敷 | |
| 2022.12.18(日)開催、制約なく熱戦。当会会長特別賞をチーム「無認可ロボ研(矢部遼、大山泰河)」に授与。 | |
| ・人材育成事業 | |
| (1)12月16日(金)第62回担当者会議(2023年度講座スケジュール確認)。(2)倉敷税務署にインボイス制度の適格請求書発行事業者登録申請。年内にインボイス適格事業者登録予定。(3)新型コロナの5類変更検討を受け、アフターコロナ対応調査を加速(タブレット教育の見積、受講条件への影響調査、人材育成チームの水江移転を想定したケーススタディ実施)、(4)12月末までに出前・共催23と体験型19を含む86講座を実施、受講者数は延べ2204名。年間では、出前・共催30とホーム78を合わせ108講座を実施、延べ2678名が受講見通し。増益の一部を講師と社員の一時金増額として支給。 | |
 | |
| 「非認知能力という力の育成と評価について」 | |
|
岡山県教育委員会「教育時報」第74巻12号巻頭に掲記論文が掲載された。著者は岡山大学教育推進機構准教授 中山芳一氏である。経歴を見ると9年間学童保育指導員を務め、学童保育研究の重要性を感じて岡山大学大学院に入り直した変わり種である。日ごろ認知症を心配している身として「非認知能力」なる言葉につい反応してしまった。「自信を持とう!」、「人にやさしくなろう!」、「豊かな心、たくましい心、根気、やる気、元気」といった数々の言葉は幼稚園、保育所、学校で普通に溢れている。現在では、こうした「心」や「気」と呼ばれるものが、わが国に限らず世界的に「非認知能力(non-cognitive skills)」という呼び名で広く認識されるようになっている由である。この言葉は、テストで点数に出来ない力の総称として使われているが、アメリカの経済学者たちが学力に偏った学校教育政策に異議を唱える中で「学力ではない力」のことを非認知能力としたことに端を発したものの様である。ノーベル賞経済学者J.J.ヘックマンが就学前の子供たちの非認知能力を育むことで、以降の基礎学力、収入、持家率にポジティブな影響を与えるという研究結果を発表してから世界各国の注目が集まった。また、2015年にOECDも非認知能力と捉えられる「社会情動的スキル」が、認知的スキルにポジティブな影響を与える調査結果を示したためにますます注目を集めるようになった。ここまで読み進むと、非認知能力重視の観点は、いかにも功利的な考えの様に感じられるが、「認知能力向上に及ぼす非認知能力の影響」という見方に置換えてみると私にも合点が行くところがある。幼時から老年に至る経験を振り返って見ると、勉強でもスポーツでも到達点を決めるのは、99%の人にとって「天賦の才能」よりも「心や氣を産み出す性格(感受性)」である様に思う。これに影響を及ぼす人物および/またはデキゴトロジーが必ず登場するのである。「三つ子の魂百まで」は、三歳前後の脳内シナプス密度が最も高く、シナプスの出会いが活発に起こることを脳科学に先んじて言い当てたもので、「感受性」や「思考力」、さらにはその後の可能性において「脳の発達」が最も活発な時期であることが検証されている。幼時体験と感化は大切であるが過去は変えられない。残念!【kajix】 | |